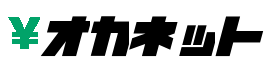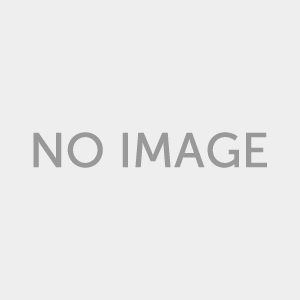ここ近年の大卒初任給の傾向
大卒の初任給は1990年以降緩やかな上昇傾向にあります。
物価の価値を同じ水準に換算して比較をした場合には1980年代より上昇傾向にあることがわかっており、一貫して新卒の給与については安定的な環境に置かれていると言えます。
大卒の初任給の調査は厚生労働省による賃金構造基本統計調査によって毎年行われており、各年次ごとに数値が公表されています。
調査が開始されたのは1968年からで、当時は月給3万600円だったものが2016年度には21万313円にまであがっています。
1960年代~1980年代までは物価が大きく高まった時期ということもあって額面の上昇はかなり急激なものとなっていますが、実質的には1974年をピークに一旦落ち込みを見せ1980年代から再度上昇に転じています。
ただしこの調査は東証一部上場企業を中心に行われているので、地方の中小企業などにおいては上記のような数値がそのまま貰えるとは限りません。
企業によっても動向が分かれており、2015年~2016年の間の変化として東証一部上場企業227社のうち66.1%が据え置き、33.9%が全学歴引き上げとしています。
2014年~2015年の間の変化に比べて全学歴引き上げをした企業の数は6ポイント減少しているので、額としては上昇しているものの全ての企業がくまなく右肩上がりであるというわけではなさそうです。
大卒以外の初任給の状況について
大卒以外の初任給について2016年度の統計を見てみると、大学院卒修士で22万7505円、短大卒で17万7822円、高卒で16万4894円となっています。
こうしてみると学歴によって大きな差がついており、特に高卒・短大卒に比べて大卒の初任給がかなり高いということがわかります。
そこで問題になるのが、果たして大卒の平均的な初任給で十分に新社会人は生活をしていくことができるのかということです。
額面の給与額が20万円前後の場合、社会保険料などを差し引かれたあとの手取り額は17万円程度となります。
ですので一人暮らしをしている新社会人はその17万円の中から、家賃や光熱費、食費、遊興費といったものを捻出していくことになります。
つつましく生活をしていけば十分な額のようにも思えるところですが、そこにのしかかってくるのが「奨学金」です。
大学卒業ができたとしても、そのときの学費を借り入れ型の奨学金によってまかなっていた場合、卒業10年以上に渡り月々1万5千円~2万円の返済をしていかないといけません。
都内一人暮らしで自由に使える額が15万円程度ということになると、かなり厳しい生活をしていくことになると言えます。