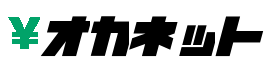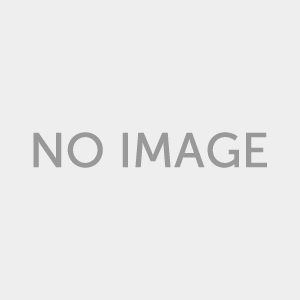仮想通貨にも税金がかかるので注意
仮想通貨は商品を購入するために使うこともできますが、多くは投資対象として用いられています。
仮想通貨取引所において売買取引をすることによって、売買差額による利益を得られます。
所得が発生したらどんな内容であっても税金がかかるというのが常識ですので、仮想通貨取引でも利益を出せたら税金の支払いをしないといけません。
基本的には、年間で20万円以上の所得が出た場合にその分が課税対象となります。
税金の種類としては所得税となり、その中でも雑所得という科目に分類されます。
また、所得税がかかると住民税もその所得額によってかかってきますので、両方の税金について考えておく必要があります。
仮想通貨取引の確定申告について
仮想通貨取引で利益が出た場合、原則として確定申告をしないといけません。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収支をまとめて、それを次の都市の3月15日までに税務署に申告するという制度です。
つまり、自分で取引記録などをまとめて税額を計算して、納付までをしないといけないのです。
会社員の場合は、毎月源泉徴収という形で、会社が計算や納付を行い、それぞれの給料から天引きしているので確定申告をする必要はありません。
しかし、仮想通貨取引は自分個人でしているものですので、すべて自分で処理をしないといけないのです。
確定申告は義務ですので、これをしないと罰則を受けることになります。
本来収めるはずだった税額にプラスして追徴課税を受けたり、最悪の場合刑事罰を受けたりします。
仮想通貨取引をするに当たっては、取引所に取引口座を開設するのが一般的ですが、多くの取引所でマイナンバーの提出が求められます。
そのため、取引記録や利益の状況は税務署に把握されています。
確定申告をしないで税金逃れをしようと思っても無駄ですので、法令を守りしっかりと確定申告をしましょう。
仮想通貨にかかる税金の計算方法
上記のように、仮想通貨にかかる税金は雑所得にあたる所得税です。
所得税は累進課税という制度で、所得が増えるごとに税率が上がるという仕組みになっています。
具体的には年間195万円以下の所得であれば税率は5パーセント、195万円を超えて330万円以下だと10パーセントといった感じで順次上がっていきます。
そして、4,000万円オーバーの所得で最高の45パーセントの税率が課されます。
雑所得というのは総合課税という制度で、給料などの他の所得と合算したものが年間所得として課税対象になります。
それぞれの所得金額に応じて控除があるとはいえ、それなり高い税金がかかることになりますので、事前に税率についてはよく理解しておくべきです。
そうしないと、税引きで利益が失われてしまう結果になりかねません。